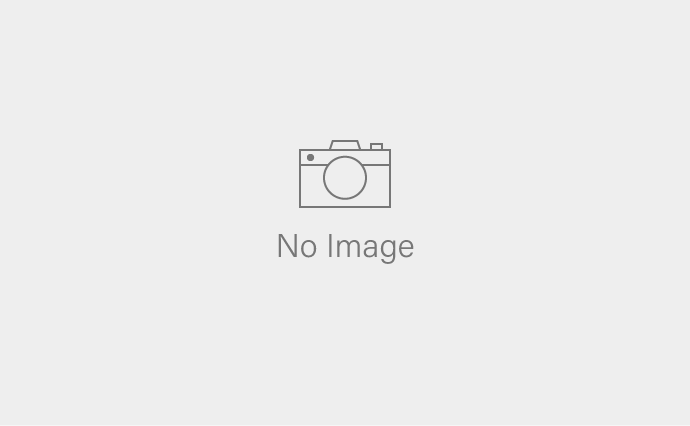相続開始後すぐに遺産分割協議を行うことにより不都合が生じて、トラブルになってしまうケースもあります。
そんなトラブルを予見して、遺言により遺産の分割を一定期間保留させることができます。
民法908条:被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺産分割の禁止を活用するケース
(1) 相続人に未成年者がいる場合
未成年者とその親権者が共に相続人となる場合は、親権者は未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。(民法826・利益相反行為)
遺産分割に特別代理人を介入させず、未成年である相続人が成年に達した後に、その者に自ら遺産分割協議に参加してもらいたいと望む場合には遺言書に遺産分割の禁止期間を記載することも有効です。
(2) 相続人が冷静になってから遺産分割協議をしてもらいたい場合
相続開始直後は、被相続人や相続財産に対する思い入れが強くなってしまい、感情的な対立が生じやすく冷静な協議が難しい場合があります。
各相続人が落ち着いて協議ができるようになるまでの冷却期間として、遺産分割の禁止期間を設けることも、紛争を未然に防ぐ手段です。
(3) 家族には伝えていない子供がいる場合
過去に婚姻関係にない相手方との間に子供を授かり認知をしている場合で、後にその子供(非嫡出子)の存在が明らかになるなど、相続関係が複雑になることが想定される場合など。
遺言による遺産分割の禁止期間
遺言による遺産分割の禁止期間は、相続開始の時から最大で5年です。
分割の禁止の対象
遺産の全部または一部でもかまいません。
相続税申告との関係
相続税の申告は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行はなければなりません。
遺言により遺産分割が禁止されていたとしても、相続税申告・納付期限が延長されることはありません。 この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課される可能性もあります。
遺産分割が禁止された状態で相続税申告を行う場合は、法定相続分に従って、期限内に相続税の仮申告を行います。
その後、遺産分割禁止期間が解除され、遺産分割が完了した段階で、確定した相続財産に従い更正の請求・修正申告を行います。
相続税減税の特例をうけるには
遺産分割が未了のままで相続税申告を行うと、相続税減税の特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)を受けることができません。
ただし、相続税の仮申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで、遺産分割後に特例の適用を受けることが可能です。
また、3年以内に遺産分割が未了の場合は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産分割が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
減税の特例を受けれるか否かについては、相続税額が重要になってきますので、専門家である税理士に相談することをお勧めいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イノウエ行政書士事務所
神奈川県相模原市中央区星ヶ丘2-5-2
行政書士 井上 勝
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意事項
記載内容には慎重を期しておりますが、執筆日以降の法改正などにより内容に誤りが生じる場合もございます。
当事務所は、本記事の内容の正確性に関しましてはいかなる保証もいたしません。
万一、本記事のご利用により閲覧者様等に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。